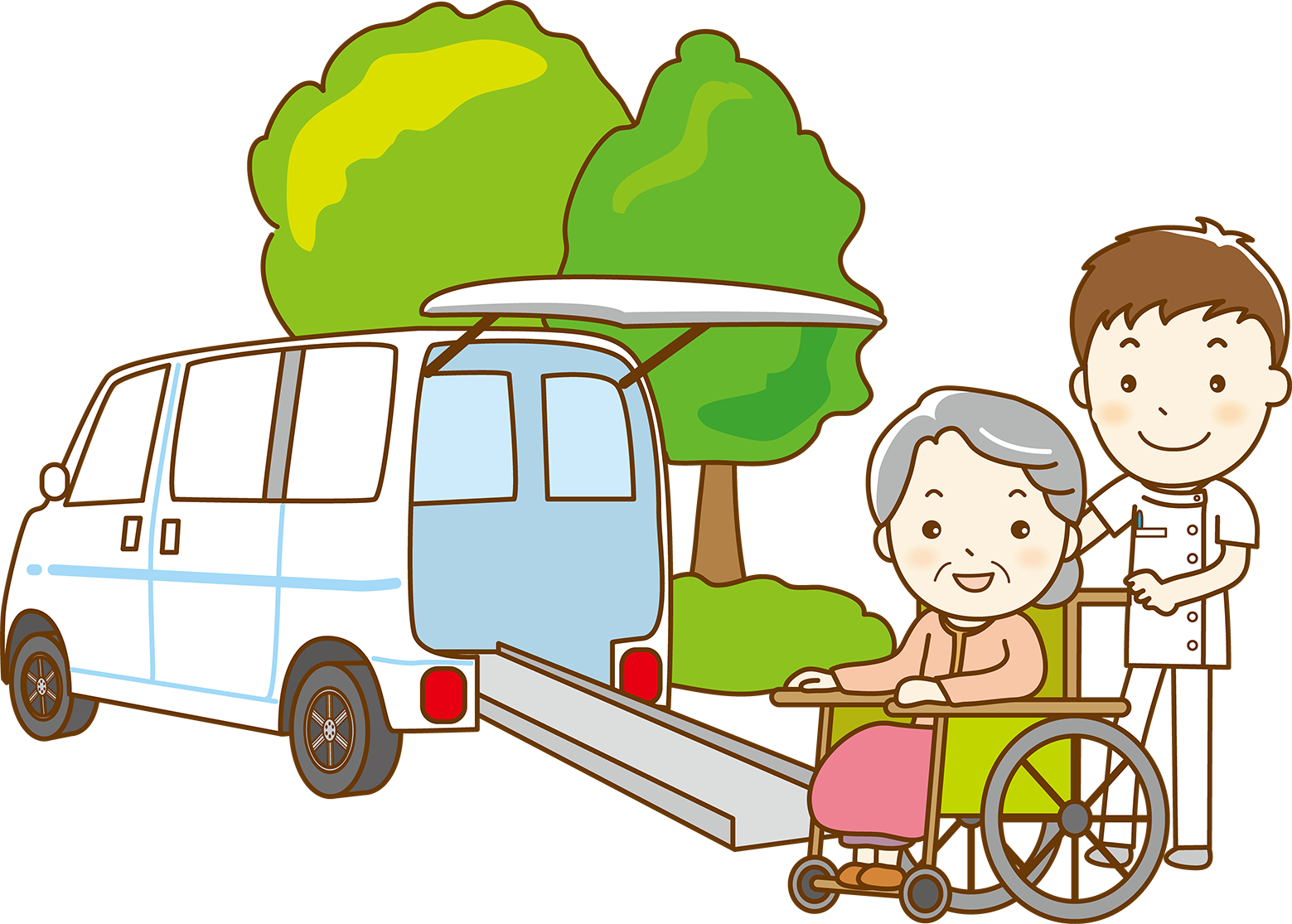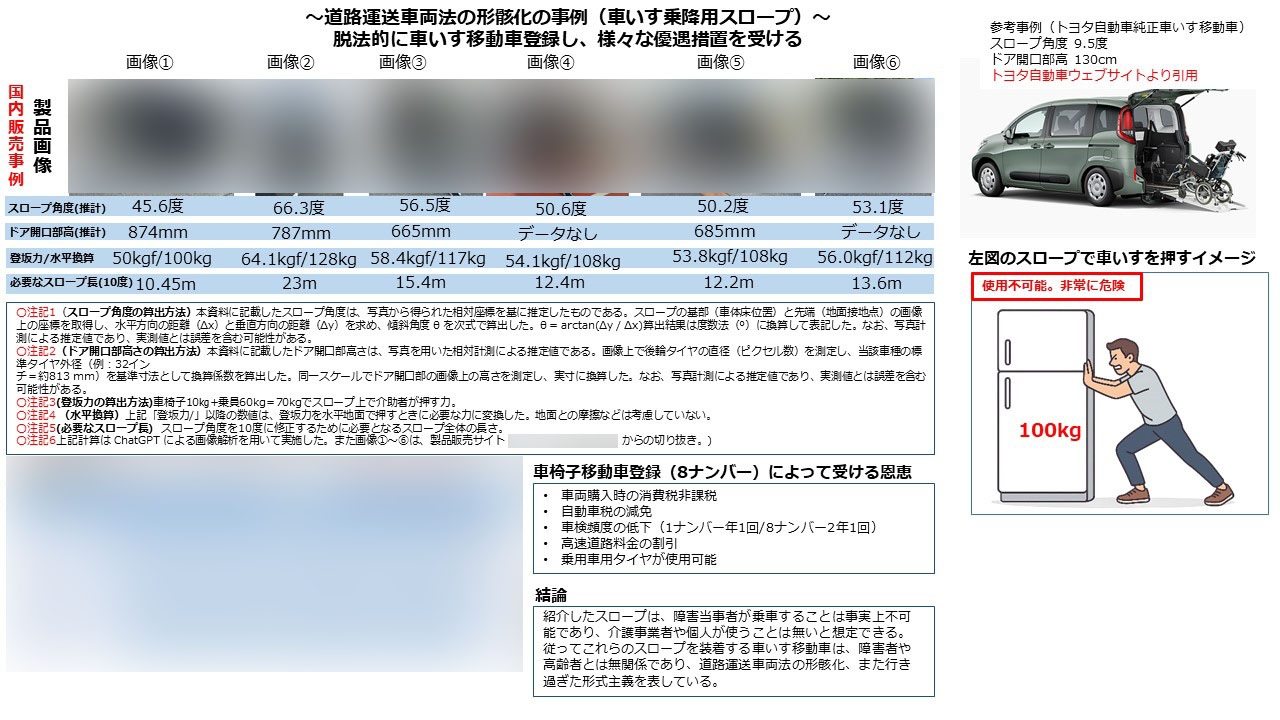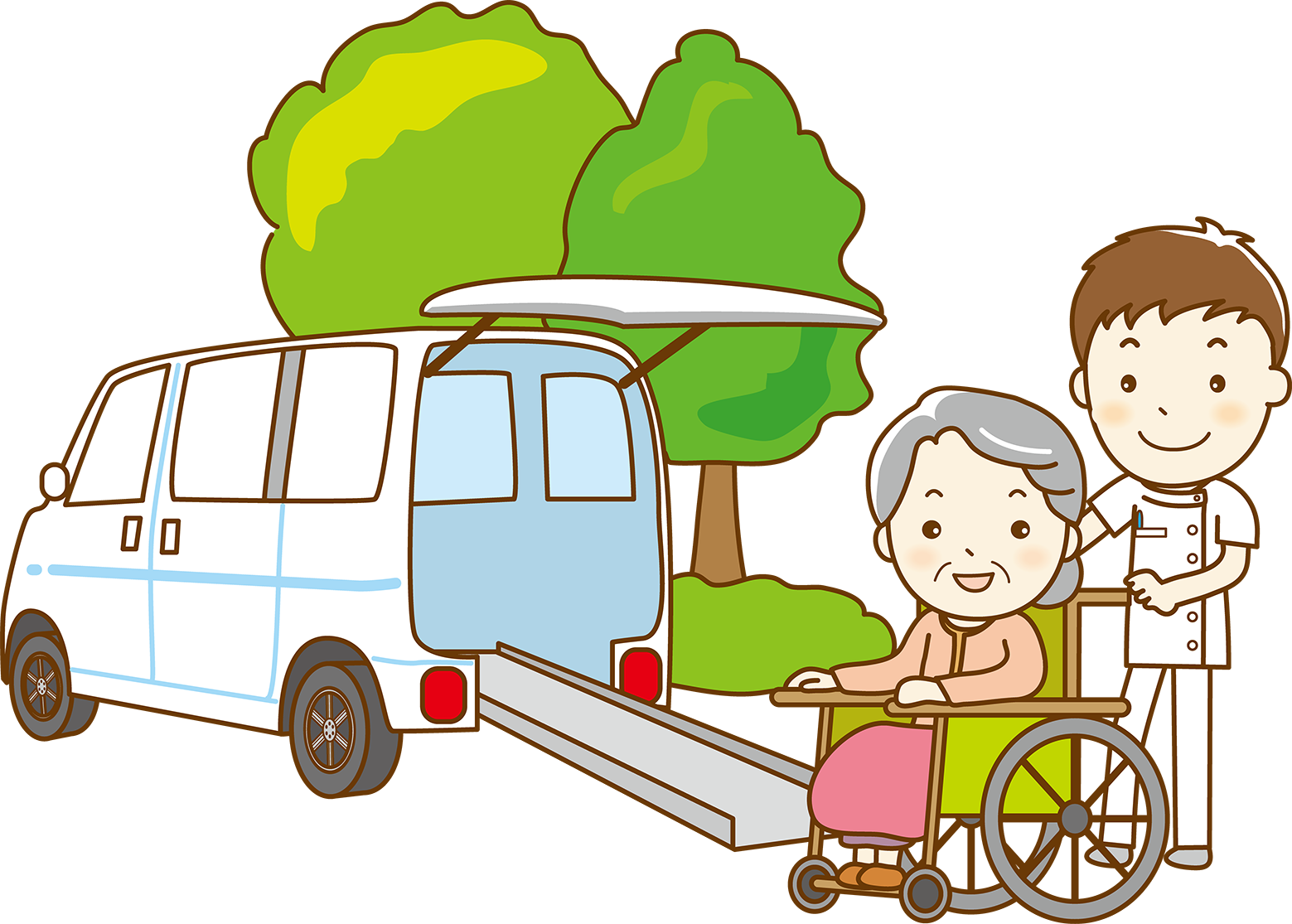wikipediaより
ジャパンタクシーの経緯
東京オリパラの開催に合わせて、ユニバーサルなタクシーを日本中に走らせるために、2017年にジャパンタクシーは生まれました。
特に通常の乗車スペース(後部座席)に車いすのまま乗車可能な構造は、日本の車いす利用者にとって希望の光となったはずです。
私もある販社から依頼を受けて、発売前の内覧会に招かれて、タクシー事業者の前で講演した経験があります。
その時の講演で私は、ジャパンタクシーという道具だけを走らせても、宝の持ち腐れになるだけで、ドライバーの意識改革が欠かせないと主張しました。
ジャパンタクシーは発売後、特に電動車いすの乗客に対応できないという欠点が当事者から指摘され、政治的なテーマにもなる事態となりましたが、現在では乗車用スロープの耐荷重設計を見直して、重量のある電動車いすでも乗車可能な車両に改定されています。(全ての電動車いすが乗車できるわけはありません。乗員の体重が加味されます)
タクシーは乗るのにお金がかかります。それも必ずしも安くはない。だから貧困に苦しんでいる人はそもそも対象外の移動手段です。そのことは大きな問題を含んでいますが、そうであっても、車いすのままタクシーに乗れることは、多くの障害者に恩恵をもたらすだろうと、私は考えていたのです。
実際に当会が行う医療従事者向け研修会でも、ジャパンタクシーを紹介しており、自家用車を手放した障害者や高齢者の移動の利便性を高める道具として、患者に進めるように言っているのです。
発売から5年ほど経って、車いすユーザーに恩恵があったのかと問われると、首をかしげてしまう、というのが私の実感です。
データがないので私の空想でしかありませんが、ジャパンタクシーに車いすごと乗る乗客はほとんどいないのではないかと思うのです。
確かに、乗り降りに異常な手間と時間がかかる。運転手の配慮が足りない。乗降する場所に制限がある。などなど、数えきれない不満が思いつきます。
しかし、トヨタ自動車というエリートが集まる会社の研究職が、なぜそんなことにも気づかないまま開発したのか?不思議でなりません。
そして、それらが事実ならば、その理由は何だろう?と私は考えてきたのです。
理由はいろいろあると思います。
挙げればきりがないのですが、最近、ある出来事にあって、なるほどなあ。と納得したのです。前置きが長いですが、今日はその出来事についてご紹介します。

wikipediaより
目的なき事業計画
先日、ある企業の新規事業に関する企画書を拝見する機会がありました。輸送システムに関する事業を展開する企業が行う、病気や障害のある人を対象にした事業です。
そして、事業を始めるにあたっての意見を求められ、企画書が送られてきました。
それを拝見して、まずに気付いたのが、その企画書には事業の目的が書かれていなかったのです。
事業とはおおよそ、何かの目的を達成するために行われます。その目的が書いていないのです。
私は一般企業の事業企画書を見る機会は初めてでしたが、中央省庁等が作る企画書は良く手にします。そして、その企画書の冒頭には大抵事業の目的が書かれています。
そこで問い合わせてみると、「企業価値を高める」のが目的だと返事が返ってきたのです。
私はそれを聞いて驚きました。病気や障害のある人を対象にした事業の目的とは、当然のことながらそれら当事者への便益であるはずだと、私は考えていましたが、そうではなく自分の会社の価値を高めるのが目的であることに驚いたのでした。「そもそも当事者のことは二の次なのか?」
結局私は、この企画書に対する意見を述べるのを断念しました。言っても無駄だろうと思ってしまったのです。
手段が目的へと逆転する
この経験から私が感じることは2つあります。
一つ目は「道具が高度化すると不可避的に目的と手段が入れ替わる」というイリュールやイリイチの言葉を思い出します。会社という、何らかの公益を追及する道具の、内部構造の複雑さが増し、仕事の進め方が高度化する時、イリイチの予言の通りのことが起こるのだと。
もう一つは、このような会社はきっとここだけではないだろう、日本中の会社、いや日本そのものがそうに違いないと確信したのです。
あらゆるビジネスや、法律や制度は、現在、改定すればするほど、益よりも不利益が増大していると感じる方は少なくなのではないでしょうか?法律や制度も、特定の目的を達成するために人間が設計した道具なのです。
それは規模の大小に関わらず、高度化した企業や社会が必ず陥る罠だとイリイチは指摘しています。
そう考えた時、どうしてジャパンタクシーは役立たずなのかを考えるヒントが見えてきます。
私はジャパンタクシーの開発と販売についての企画書を見ていませんが、
もしかするとその文書の中には「当事者の利益」について明確に書かれていなかったのではないか?二の次になっていたのではないか?と想像してしまいます。
ユニバーサルというわが国では新しい価値を、タクシー車両の販売を通じ、オリンピックという場を通じて世界に発信し、自分の会社、及び国家の価値を高める。
もしそうであれば、つまり、当事者のためではなく、自分の欲を満たすために作った車だといえます。これでは当事者の益になるはずがありません。そもそもそのような目的で作られた車ではないのですから。
わたしは、このブログで特定の企業を攻撃する意図は持っていません。私が言いたいことは、このような目的と手段が入れ替わる、ということは、どんな道具にも起きるし、現に起きているという現実を自覚することの大切さと、困難さについてです。
病院も、患者の疾患を治療するという目的を持った一つの社会的な道具です。それが複雑化、高度化した時、上記と同様の目的と手段の転換が不可避的に起こる。
研修会の中でも触れていますが、運転評価もいつの間にか目的と手段が入れ替わるという事が起きました。
評価の目的は「運転免許が更新の可否」です。しかし、現在シミュレータや実車評価によって、実際に患者が安全に運転が出来るかどうかが、評価の目的に変ってしまっています。
その理由は明確で、評価の手法を改良する試みが高度化することによって、目的と手段が入れ替わった。シミュレータや実車評価は、本来は診断書作成のための手段の一つでしたが、今はそれが目的となり、免許更新の可否を検討するのではなく、実際に安全な運転が出来るかどうかを評価する、というシステムになってしまいました。そして、このような転換は、やはり患者にとっては不利益でしかないのです。
道具=システムの中で働く人たちはその道具を俯瞰して見ることが苦手なものです。
それは地球が青い色をしていることを人間が知るためには、地球の外へ出るほかなかったのと同じでしょう。
なぜ俯瞰することが苦手なのか?
それは、人間とは高度な道具の内部では歯車化してしまうから。
イリイチは、目的と手段が転換すると、当初想定した便益を遥かに超える不利益が、当事者に及ぼされると警告しています。
私たち現代人は、システムという道具から逃れることが出来ません。
だからこそ、俯瞰する思考が重要だと思うのです。